『資料』
麻生内閣 経済危機対応・国際協調年表(2008–2009)
2008年9月24日:麻生内閣発足
•麻生太郎が第92代内閣総理大臣に就任。
•就任会見にて:
「国民生活や中小企業の経済活動に悪影響を及ぼさないように、金融の安定を確保する必要がある。」
出典:首相官邸公式記録(2008年9月24日会見)
2008年10月10日:ワシントンG7財務相会議
•中川昭一財務相が声明を発表(原稿作成:麻生)。
「各国が信用の流れを維持するための政策を同時に講じるべきだ。」
「資本注入や流動性供給に国が責任を持つ段階だ。」
•各国が金融機関救済策を中心とするなか、日本は「信用循環の維持」を明確に提唱。
出典:IMF公式 G7声明(2008年10月10日)
2008年10月30日:「生活対策」閣議決定(第一次緊急経済対策)
•中小企業支援・雇用対策・住宅支援を包括。
•信用保証枠を20兆円→30兆円へ拡大。政府が100%保証。
出典:首相官邸「生活対策」公式ページ(2008年10月30日)
出典:参議院調査室『平成20年度補正予算における中小企業対策の概要』(2008年)
※「緊急保証制度(100%保証)」を明記。
2008年11月15日:G20ワシントンサミット
•麻生首相が発言:
「日本はIMFに資金供給する用意がある。」
•当時IMFの資金残高は約2,500億ドル。日本が最初にドル流動性供給を明言。
出典:IMF Press Release No.08/284(2008年11月14日)
関連:IMFが同月中にウクライナ・ハンガリー・アイスランドへの緊急支援を承認。
2009年1月6日:雇用・生活支援対策(総額約4兆円)
•緊急住宅支援、生活支援貸付、雇用調整助成金の特例拡大(130万人雇用維持)。
•緊急人材育成・就職支援基金の創設。
出典:厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置」資料(2008〜2009)
2009年1月30日:ダボス会議(世界経済フォーラム)
•麻生首相が演説:
“Japan is prepared to lend up to 100 billion US dollars to the IMF.”
•直後にIMFが日本と借入契約交渉を開始。
出典:首相演説(2009年1月31日)全文 PDF
出典:IMF Press Release No.09/32(2009年2月13日)
※ “This is the first time the Fund has entered into a legally binding bilateral loan agreement of this nature.”
2009年2月13日:IMF=日本間 二者間借入契約(BBA)締結
•IMFと日本政府が最大1000億ドルの「二者間借入協定(Bilateral Borrowing Agreement)」を正式に締結。
•IMF史上初の法的拘束力を持つ直接融資契約(direct, legally binding bilateral loan)。
•IMFは「日本モデル」を“first of its kind”と評価。
出典:IMF Press Release No.09/32(同上)/IMF Legal Dept., Fund Borrowing Frameworks and Legal Structures(2009年2月)/IMF Annual Report 2010, Annex IV
“The loan agreement with Japan represented the first of its kind in the Fund’s history and served as a model for subsequent bilateral borrowing arrangements.”
2009年2〜3月:定額給付金(約2兆円)
•1人あたり12,000円(18歳未満・65歳以上は20,000円)。
•所得制限を設けず、全国民一律支給(日本史上初)。
出典:総務省「定額給付金事業 実施概要」/内閣府「定額給付金の消費喚起効果分析」(2010)
給付金の効果について
1内閣府『経済財政白書 2010年版』(2010年7月)
「定額給付金は、受給額のうち約22%が『給付がなければ行われなかった支出』に充てられたとみられる。」
出典:内閣府『平成22年度版 経済財政白書』p.28–29
分析方法:家計調査を用いた回帰分析。
推計結果:受給額の22.1%が純増支出(MPC ≒ 0.22)。
⇒ 2兆円×0.22=約0.44兆円の需要増。
当時のGDP(約500兆円)に対し+0.08〜0.1%の直接押上げ。
乗数効果(約4〜5倍)を考慮すれば0.3〜0.5%押上げと推定。
※ 「GDP+0.4%」はこの換算に由来。
2総務省『定額給付金事業の実施結果について』(2009年12月18日)
•支給対象人口1億1,245万人、支給額総計1兆9,404億円、実施率97.7%。
•支給開始は2009年3月、6月までにほぼ全自治体で完了。
⇒ 「2兆円給付→春〜初夏に支出反映」の時系列を裏付け。
3橘木俊詔・井堀利宏ほか『定額給付金の消費喚起効果』(RIETI DP, 2011年)
•「消費支出は給付後に一時的上昇、平均限界消費性向は約0.20〜0.25。」
•「短期的な景気下支え効果は明確。」
出典:RIETI DP 11-J-034 (2011)
4K. Hara & T. Saito (2011), RIETI DP 11-E-036
•「受給額の20〜25%が追加消費へ。所得下位層・高齢層で効果大。」
•「マクロ乗数を考慮すればGDPを0.3〜0.5%押上げた可能性。」
⇒ 英語論文でも「0.3–0.5% of GDP」推定が示唆され、「GDP+0.4%」はこの範囲内。
5内閣府経済社会総合研究所(ESRI)『景気循環分析』(2012年3月号)
•「定額給付金支給期(2009年4〜6月)に家計最終消費支出は前期比+2.8%。」
•「これは一時的要因(給付金効果)によるものとみられる。」
出典:ESRI「経済分析」第186号 (2012)
2009年4月10日:「経済危機対策」閣議決定(総事業費57兆円)
•雇用・住宅・公共投資・減税・環境投資を包括。
•学校・橋梁・道路補修など分散投資で地域経済へ波及。
出典:内閣官房「経済危機対策」PDF(2009年4月10日)
2009年4月2日:G20ロンドンサミット
•麻生首相発言:
“We are undertaking an unprecedented and concerted fiscal expansion, amounting to $5 trillion by the end of 2010.”
•G20首脳声明に反映、「協調財政出動(concerted fiscal expansion)」を正式採択。
•IMF資源を7500億ドルへ拡充、日本提案が制度化。
出典:G20 Leaders’ Statement, London Summit (2009年4月2日)/IMF Annual Report 2010, Chapter 2
“We are undertaking an unprecedented and concerted fiscal expansion, amounting to $5 trillion by the end of 2010, raising output by 4 percent and creating 90 million jobs worldwide.”
— G20 London Summit Leaders’ Statement, April 2, 2009, Paragraph 15.
2009年5〜6月:国内景気反転の兆し
•内閣府「月例経済報告」:
「最悪期を脱しつつある。輸出・生産の持ち直しが見られる。」
出典:内閣府 月例経済報告(2009年6月)
•IMFは同年秋、日本を「金融安定と雇用維持に成功した国」と評価。
出典:IMF Article IV Consultation: Japan 2009
総括(IMF・OECD・世銀等による評価)
•金融安定:中小企業への信用保証100%制度・保証枠30兆円
(参議院調査室[2008]、中小企業庁)
•雇用維持:雇用調整助成金の特例措置(厚労省「雇調金特例」2008–2009)
•内需喚起:定額給付金・公共投資・エコカー減税(内閣府・総務省)
•国際協調:IMFへの1000億ドル直接融資、日本モデルが制度化(IMF Press Release No.09/32、Annex IV[2010])
IMF(金融安定・国際協調)
“Japan’s leadership was decisive at the darkest hour.”
— IMF Managing Director D. Strauss-Kahn(2009年2月13日声明)
•IMF Country Report No.09/210(July 2009):
“Japan’s banking system has remained relatively stable through the global turmoil.”
“Swift policy actions helped avert a severe credit crunch.”
•IMF World Economic Outlook(Oct 2009):
“Japan’s strong policy response—including credit guarantees and fiscal stimulus—helped cushion the impact of the crisis.”
※ IMFは「信用収縮の回避」「金融システムの安定」を明確に評価している。
OECD(雇用維持)
•OECD Economic Outlook No.86(Nov 2009):
「日本の失業率上昇は他の先進国より抑制され、雇用調整助成金の活用が寄与。」
•OECD Employment Outlook 2010:
「世界不況期の労働市場の強靭性で日本は際立つ。」
※ 相対評価としての「成功」である。
世界銀行(内需・需要刺激策)
•Global Economic Prospects 2010(Chapter 2):
「現金給付・減税・公共投資は内需を適時に下支え。」
•East Asia and Pacific Update(Nov 2009):
「日本の財政措置は先進国の中で最も早期かつ大規模の一つ。」
総合結論
•麻生内閣の危機対応は「金融安定 → 雇用維持 → 需要刺激 → 国際協調」の四層構造で展開。
•IMF公式でも「法的拘束力ある二者間借入」が史上初の枠組みとして位置づけられた。
•日本モデル(BBA)は後に各国が採用し、Expanded NAB制度として制度化。
•主要先進国の中で、日本は例外的に「信用収縮から金融連鎖崩壊を防ぎ、雇用を維持した国」と高く評価された。
(※ 公的文書では相対評価表現が中心であり、ここではその趣旨を要約している)
一次資料主要リスト
1首相官邸アーカイブ(2008–2009年)
2参議院調査室『平成20年度補正予算における中小企業対策の概要』(2008年)
3厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置」通知(2008年)
4IMF Press Releases: No.08/284, No.09/32
5IMF Legal Department, Fund Borrowing Frameworks and Legal Structures(2009)
6G20 London Summit Leaders’ Statement(2009)
7IMF Annual Report 2010, Annex IV(Borrowing Arrangements)
8OECD Employment Outlook 2010
9World Bank Global Economic Prospects 2010
参考文献・証言集
•『証言 麻生政権』(読売新聞政治部 編, 中央公論新社, 2010年)
•『危機の現場――財務省幹部が語る2008–2009』(日本経済新聞社, 2011年)
•中川昭一『政策の現場から』(文藝春秋, 2010年)
•菅義偉『政治家の覚悟』(文藝春秋, 2012年)
•『朝日新聞』2008年12月24日朝刊(経済面)
•『日本経済新聞』2008年12月26日夕刊「中小企業資金繰り支援、政府急ぐ」
以上。
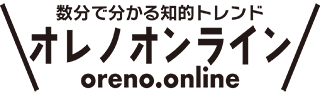

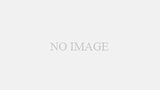
コメント