『麻生政権の経済対策の解説』
● リーマン・ショックは日本に影響がないという誤解
当時のマスコミや一部の経済学者、政治家(財政担当の与謝野特命担当大臣を含む)は、リーマン・ショックの日本への影響は限定的であると発言していた。
理由は「日本の銀行がサブプライム関連資産をほぼ保有していなかった」ためである。
ただしこの見通しは、「実体経済への信用収縮」までは十分に織り込んでいなかった。
その点をいち早く捉え、「信用崩壊と資金繰りのリスク」を理解していたのが麻生であった。
政権発足当時、製造業・建設業・運送業などで「黒字なのに現金がない(資金ショート)」ことによる倒産(いわゆる黒字倒産)が見受けられた。
麻生は商社・経営者出身であり、帳簿上の数値だけでなく現場の資金繰り感覚を備えていた。
企業は売上から入金までに数ヶ月のタイムラグ(手形決済)が生じる一方、その前に給与や仕入・外注の支払いがある。
それを埋めるのが運転資金としての融資である。
世界から資金が引き上げられると金融システムの信用が収縮し(貸し渋り)、中小企業は「信用で回っている」ため連鎖倒産の危険が高まる。
当時の麻生の発言として「中小は日単位で潰れる」「年末の餅代が払えない企業が出てくる(年末が最も危険)」がある。
この局面認識は各国の初期対応の差にも表れている。
•米国:銀行救済、不良債権買取、量的緩和(銀行を救済し貸出再開を促す)
•英国:銀行国有化、住宅ローン保証(銀行破綻回避を最優先、企業・雇用対策は相対的に手薄)
•ドイツ:金融安定基金、雇用調整補助金(銀行対策と雇用維持。中小資金繰りは後回しの傾向)
•フランス:銀行保証、公共投資(銀行支援と内需拡大。対応の立ち上がりは相対的に遅い)
•中国:60兆円規模のインフラ投資(大規模だが効果発現に時間)
•韓国:米・日との通貨スワップ、IMF連携(為替防衛に注力、国内産業対策は限定的)
•日本:中小企業信用保証、IMFへ1000億ドル融資(国内外の信用循環の維持)
麻生が最初に打った手は資金の直接供給ではなく、政府による信用保証であった。
銀行が企業へ融資した金を政府が全額保証する制度を拡充し(中小企業庁・金融庁が全国銀行協会に「貸し剥がし禁止・貸出維持」を通達)、実体経済の決済・雇用を止めないようにした。
結果として、日本では連鎖倒産の大規模な波は発生しなかったと評価できる。
要するに、他国が銀行への公的資本注入で金融破綻を防ごうとする間に、麻生は「政府保証で見せ金(信用)を積む」ことで信用連鎖崩壊を未然に抑制したのである(実際に保証が全額発動された金額は限定的であった)。
結果、銀行の破綻も回避された。
● 金融崩壊が信用崩壊に転化すれば世界恐慌になると認識
麻生は、金融システムの危機の本質を信用の破綻(連鎖破綻)と捉えていた。
商社マン・経営者としての経験から、金融市場の空気感を体感として理解していたといえる。
現代金融は現金の手渡しではなく相互の信用で成り立ち、「そこにあるものとする」という約束(制度・期待)の上に築かれている。
危機局面では市場は心理で動き、約束が守られないとの疑念が広がれば「負の連鎖」が始まる。
こうなると政府が資金を供給しても投資家心理は容易に戻らない。
ゆえに麻生は、資金を動かすより先に“信頼を見せる”方が迅速かつ効果的だと考えた。
しかし国際社会の初期対応は、目の前の金融機関の破綻回避に偏重しがちであった。
麻生は外相時代に経験したアジア通貨危機を念頭に、IMFの対応遅延が連鎖破綻を招きうることを認識していた。
このままではIMF資金が枯渇し、韓国、東南アジア、中東、東欧などに危機が拡散する公算が大きい。
それは日本企業の取引相手国にも及び、日本経済への波及が避けられない。
そこで麻生は即座にIMFへの融資を表明し、まず国際社会に対してIMFの信用を回復させた。
実際、当時の他国は政治・財政面で身動きが取りにくい状況にあった。
このタイミングでの決断は、日本の国益を守る現実主義的外交でもあった。
結果として日本のIMF投票権は一時的に上昇し、米欧の間で金融外交のプレイヤーとして存在感を回復した。
麻生にとってこの融資は「世界の信用を守る」だけでなく、「日本の国際発言力を取り戻す」戦略でもあった。
麻生は国際協調主義(リベラル・インターナショナリズム)の理念先行型というより、保守的リアリストと位置づけられる。
理想ではなく実利を基軸に、“世界を救うため”に見えても根底には日本の国益を担保するという立場である。
● なぜ、総額110兆円もの経済対策が可能だったのか
財務省は一般に、
1短期的なバラマキ
2国債増発
3政治判断による即興的財政支出
を嫌う。
麻生の経済対策(2008年10月〜2009年5月)はこの三要素を含んでいたにもかかわらず、財務省は最終的に全面支援に回った。
その理由は三点で説明できる。
(1)財政の“文法”で語った
麻生は国家予算の数字を正確に把握し、財務官僚の論理構文(主計局の文法)で政策を語ることができた。
「景気が悪いから金を出せ」では動かない財務省に対し、財源・規模・回収の道筋まで定量で提示して反論を抑えた。
(2)スピードを盾にした
官邸に経済危機対策本部を立ち上げ、財界・各省の意見を短期に一気に取りまとめた。
資金ショートと連鎖倒産が迫る中、反論する時間を与えない政治主導を確立した。
「財務省が一体で危機対応に入った」「主計局も政治主導を容認した」との記録が財務総研『危機の中のリーダーシップ』(2010)に残る。
(3)財務省を敵にしなかった
小泉政権や第一次安倍政権のように財務省を“抵抗勢力”として対峙せず、協働の設計に努めた。
総額110兆円の経済対策といっても、実際の財政出動は30兆円規模にとどまる。
例えば信用保証枠は一般会計に20兆円計上されるが、原則としてほぼ全額が戻る性質である。
また、IMFへの拠出は外為特会(特別会計)から行い一般会計への影響を回避、
国債増発についても建設国債・経済危機対応国債として、恒常的な赤字国債と性格付けを分けた。
(まとめ)
以上より、麻生は実務型の危機管理政治家と位置づけられる。
平時は財政規律を重んじつつも、危機時には大型の財政出動を躊躇しない機動性を発揮した。
(続く)
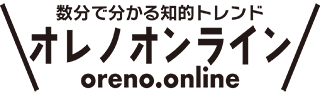

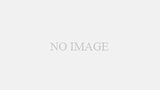
コメント